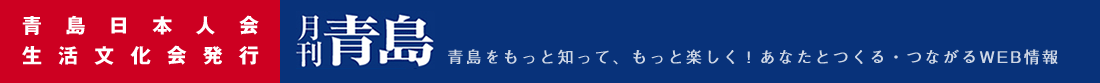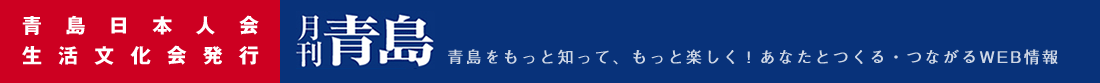茂木美保子
こんにちは!
2019年より日本人会婦人会の役員をしております茂木美保子と申します。
今回ふるさと自慢の執筆を拝命いたしまして、ふと自分のふるさとを思い返すと…東京。他の皆様の記事と比べてかなり見劣りしそうですが、頑張ります。
私が生まれたのは福岡県福岡市ですが、小学校の時に父母の本拠地である東京都品川区に戻ってまいりました。品川区といえば忘れてならないのが、日本の考古学発祥の地、大森貝塚!
現在東京近郊でも大小様々な貝塚や縄文時代の遺跡が発掘されていますが、大森貝塚は1877年(明治10年)にアメリカ人動物学者のエドワード・シルベスター・モースにより発見されました。なんでも、横浜から新橋に向かう列車の中、大森駅を通り過ぎたあたりで窓の外に貝の層を発見したとか。なんていう動体視力!
縄文時代は約1万6500年前から稲作が始まる約3000年前と1万年以上も続き、草創期〜晩期までの大体6つの時代に分かれるそうですが、大森貝塚はその後期〜晩期にかけてのもの。
現在大森貝塚は大森貝塚遺跡公園になっており、モース博士の胸像や貝塚の剥離標本などが展示されています。遊具などはない公園ですが、緑も多く子供たちの憩いの公園となっています。公園の端はJR京浜東北線・東海道線の線路と隣接していて、そこから向こうの南大井は地面が一段低く「ここから先は海だったんだなぁ…」と感じられる場所でもあります。
1万年以上も続いた縄文時代ですが、その間自然とともに生活するエコで平和な時代だったということで近年注目されていますが、実は岡本太郎は1952年に縄文土器について美術的観点から論文を書いているのだとか。
不勉強ながらこの論文については読んでいないのですが、歴史の授業で「縄文土器は模様あり、弥生土器はシンプル」ということを何の疑問もなく受け入れていたものの、ここ最近中国国内の博物館で同じくらいの年代、あるいは時代区分のものを見ても、中国の壺や器などはどれも表面がツルツルしていてキレイ!と縄文文化の特異性を改めて感じます。(ちなみに「縄文」とつけたのも、先に出てきたモース博士の論文中の「Cord marked pottery」(縄目をつけられた土器)からだそうです。)

大森貝塚だけでたくさん書いてしまいましたが、他にも品川区には最近新型コロナウィルスワクチン接種会場にもなっている大井競馬場があり、競馬だけでなく親子連れでBBQやピクニックが楽しめるほか、隣接する京浜運河沿いに作られた幅広いスポーツ施設もある大井埠頭中央海浜公園などもあり、こちらでは水場を生かした潮干狩りや釣りなども楽しめます。(小学校の遠足で行ったなぁ…)
また、お隣大田区になりますが大森繋がりでJR大森駅から出ているバスに乗って30分で城南島海浜公園や京浜島つばさ公園など、羽田空港降り立つ飛行機を浜辺から見られる公園もいくつか。

品川、というと新幹線の駅の1つというイメージが多いでしょうが(そしてそもそも品川駅は港区)、歴史あり(東海道五十三次の一の宿でもありますね!)、エンターテインメントあり、自然ありと意外とあなどれません!
わざわざ観光に…とは言えるほどではありませんが、青島←→羽田便ができた暁には「そう言えばそんなところも近くにあるんだなぁ」と頭の片隅に思い出していただけると幸いです。 |