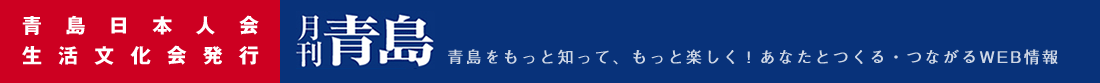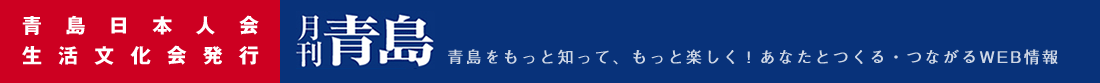大正3年(1914)年8月1日、欧州で世界大戦が始まった。日本は日英同盟に基づいて独逸に宣戦布告し青島で独逸と戦ったと聞かされているが、青島における日独戦役は実はそれほど簡単な経緯で戦火を開いたのではなかったようだ。
1.日英同盟とは?
明治32年(1899)、中国山東省で発生した「義和団の乱」は、キリスト教徒を殺害し西欧的な物を破壊するなどの暴力行為を拡大しつつ北京に入った。当時清国の実権を握っていた西太后は義和団の味方となり、明治23年(1900)、北京に公使館を置く列国に宣戦布告するとともに、清国軍を派遣して北京にあった公使館や天津の租界を攻撃させた。列国は団結して連合軍を編成し天津を攻略した後、同年8月には義和団・清国軍に包囲されていた公使館区域を開放した。この後連合国は約72,000人の軍隊を清国に派遣し義和団の掃討作戦を実行した。
明治33年(1901)9月に清国と連合国の間で和議が進められ、北京議定書が締結された。この議定書では、清朝歳入の約5倍に及ぶ4億5千万両の賠償金が課せられた。この賠償金はロシア、独逸、フランス、イギリス、日本の順に支払われ、各国は公使館警備のために清国内に軍隊を駐留することとなった。
ロシアは義和団の暴行が満州に及んだときに満州全域に軍隊を派遣したのだが、北京議定書締結後、全く軍隊を撤退しなかった。
イギリスは清国における自国利権の維持を図る上で、義和団の乱の後も満州から撤兵しないロシアを牽制したいと考えて日本に接近してきた。当時の日本は、いずれロシアとの対立は避けられないと判断して英国と同盟を結ぶことを決し、明治35年(1902)1月に第1次日英同盟を締結した。この2年後、日露戦争が勃発したのだが、イギリスは好意的中立を保ちつつ、情報収集やロシア海軍への非協力で日本を助けた。
なお、西太后は明治41年(1908)8月に逝去。明治44年(1911)に辛亥革命が発生し、明治45年(1912)には中華民国(北洋政府)が樹立された。
この後、日英同盟は明治44年(1911)に第3次まで継続更新されたが、この第3次同盟期間中に第1次世界大戦が勃発したのである。
2.日本が独逸に戦線を布告するまでの経緯
イギリスと独逸の国交が風雲急を告げだした大正3年(1914)8月1日、日本はイギリス政府に対して、イギリス・独逸が戦火を開いた場合に日本の参戦を必要とするか否か、其の意向を尋ねた。これに対してイギリス政府は、イギリスが独逸と戦うか否かについては未定であるが、仮に戦火を開いたとしても、日本の参戦は必要ないであろうと回答してきた。
8月4日、イギリス政府は独逸と開戦すること、ただし日本の援助は必要ないであろうと連絡してきた。しかるに8月7日、イギリス政府は日本政府に対して、日本海軍によってイギリス商船に危害を及ぼす独逸海軍を捜索し撃破することについて協力して欲しい旨、日英同盟の趣旨に基づいて申し入れがあった。これに対して日本政府は、イギリスを援助するのであれば単に独逸艦船を破壊するにとどまらず、東洋において日英両国の利益の脅威となる独逸の根拠地である青島を攻略する事が必要であると、イギリス政府に通知した。翌日8月8日、日本政府はイギリス政府からの回答を待たずに、独逸との開戦を決議し勅裁を仰いだ。
8月9日、日本からの通知に対してイギリス政府は、日本が独逸と開戦すると戦火は青島から中国全土に及びかねず、イギリスの通商上にも少なくない影響をもたらす事が懸念されるので、イギリス政府として在北京イギリス公使及び在中国イギリス艦隊司令官の意見を徴して閣議で決定するまで、日本の開戦を見合わして欲しい旨回答してきた。
日本政府はこのときすでに開戦を決議し勅許を仰いでいたので、イギリスの回答に接して当惑し、外務大臣がイギリス政府に対して、「日本開戦の目的は専ら海上貿易保護と独逸根拠地の掃討であること、日本の目的は極東平和の確立であって領土的要求は全くないこと、日本の開戦はイギリス政府の要請に基づくものであり、すでに勅裁済みであるから特別の事情がない限り変更不能であること、特に日本民心は明治28年(1895)の三国干渉を顧みて独逸に対して敵愾心に燃えていることから、参戦を遅疑することは国内政治上重大なる結果を予期せざるを得ない」とその苦衷を訴えた。
8月11日、イギリス政府は、在北京公使及び在中国艦隊司令官が戦局の中国本土への波及を望んでいないとして、同盟協約に基づく日本の軍事行動を当分中止し、今後の形勢を注視して欲しいとの回答をよこした。これに対して日本政府は、日本の国論はすでに開戦に傾きもはや体制を転換することは困難であるので、イギリス政府がいったん援助を求めながら後になって取り消すことで日本政府がいかなる立場に陥るか、篤と熟慮反省されたいと強硬にその反省を求めた。
8月13日、イギリス政府は日本の軍事行動範囲をシナ海の西南、北太平洋及び膠州湾に制限することで、日本の宣戦布告に同意しようと回答してきた。
ところが8月14日イギリス政府は、「日本政府から領土的野心がないことを保証されれば」前日回答した日本の軍事行動の範囲制限を撤回する旨通知してきた。
| |
なぜ、イギリス政府は日本の青島攻略に対して上述のように曖昧な態度に終始したのであろうか。それはイギリスとして「イギリスの中国における権益保護のために日本に参戦して欲しいが、日本参戦によって日本の権益が拡大することを望まない」からであったのだろう。 |
3.日本 独逸に対して宣戦布告
日本政府は、大正3年(1914)8月15日、独逸政府に対して最後通牒を発した。その内容はおおむね次の項目を独逸政府に勧告するものであった。
1)日本及びシナ海方面より、独逸艦隊を即時撤退すること。退去できない場合は直ちにその武装を解除すること。
2)独逸帝国政府は膠州湾租借地全部を中国に還付する目的を持って、1914年9月15日を限り、無償無条件で日本帝国官憲に交付すること。
日本帝国政府においては、上記の勧告に対して1914年8月23日正午までに無条件で応諾する旨の独逸帝国政府の回答を得ない場合日本帝国政府はその必要とする行動をとることを声明する。
日本政府はこの最後通牒を独逸政府に発するとともに、在日フランス・ロシア・アメリカ大使及びオランダ・中華民国公使に対して、日本はこの機会に領土を拡張する意図は存在しないことを説明した。これより先、中華民国政府(袁世凱大統領)は第1次世界大戦が勃発するや直ちに局外中立を宣言していた。
この日本政府からの最後通牒に対して、独逸政府からは回答期限までに何の回答もなかったので、大正3年(1914)8月23日に宣戦の勅語が発布され、日本政府は独逸政府に対して宣戦布告を行ったのである。
| |
日独戦役後において日本がドイツから獲得した山東におけるドイツ権益を中華民国に返還しなかった事は、日本政府の独逸政府に対する最後通牒の2)項の内容、及びこれに基づく日本政府の中華民国・欧州各国に対する説明の内容と相違して いる。そしてこのことが、20世紀前半の日本-欧米各国との外交関係、特に日本-中国との外交関係に甚大な影響を及ぼしたのだ。 |
|