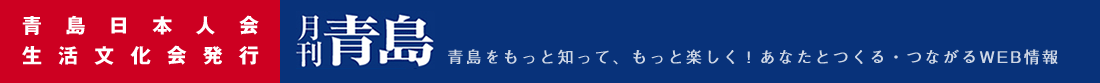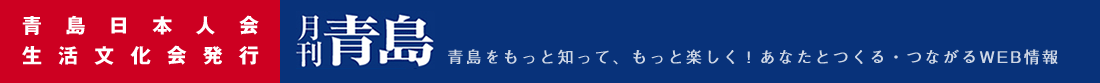コロナ禍の中で行われた東京オリンピック。ビジョンとして掲げられたのは「多様性と調和」ということで英語ではThe ”Unity in Diversity”と表現される。その象徴として聖火の最終ランナーに大坂なおみ選手がえらばれたということだ。この多様性と訳される「ダイバーシティ」が何か知らぬ内にカタカナ英語で登場し市民権を得てきた。最初に聞いた時にはどこの国の都市かとも思ったが前後の文脈からしておかしい。cityではなくsityなのだ。
ずいぶん昔のことになるが、何かの試験問題で和訳せよというのがあり、cocktailというのが長文の中に何度も出てきてしかもdrinkとある。そもそもカクテルという飲み物を知らなかったので一生懸命ニワトリのしっぽを飲むとはどういうことかと知恵を絞ったが、致し方なく何も書かないよりはマシだとそのまま書いたものであった。ちなみに中国語でも鶏尾酒と訳す。
日本人学校では、親が中国人と日本人の世帯が半数近くあり、家庭では中国語を話し、学校で日本語、それに英語もマスターしバイリンガルを通り越してトリリンガルという子もたくさんいる。かつて知り合いの台湾人で、流ちょうな日本語、それに英語、広東語、タイ語まで話せる人がいた。わたしが、後ろから頭を殴ると「痛い!」と何語で発するのだろうかと尋ねたところ
「その場で話している言葉になるでしょうね」。ということであった。実験したわけではない。が、周囲の環境に応じるらしい。
「菊と刀」で有名なルース・べネディクトが著した「レイシズム」。この人種差別の問題も多様性のなかで大きな位置を占め いまだ続いている問題だ。
ジェンダーという言葉もよく耳にする。性差ということで「男性像」とか「女性らしさ」というのがそれにあたる。オリンピックで女性のボクシングやラグビーの試合を観ていると「そこまで。。。」という気もする。男性の新体操やアーティスティックスイミング競技はされないと思うが、あっても見たくはない。しかし、文化による性差ということでは識字率の問題などあって、女性に学問は不要といった時代に育った農村の60代の女性は、街の家政婦にでて、その家の子どもに字を聞かれ「オバちゃんは字が読めないのよ!」と恥ずかしそうに言っているのを目にしたことがある。文もうというのは現代中国でもあるのだと驚いた。
身体障碍者への差別はパラリンピックなどを通じて随分緩和してきているように思える。いずれにせよ時代の趨勢は弱きを助け、公平さを旨として動いているようだ。コロナも人種、民族、年齢、性別、宗教などに関係なく地上を覆っている。 (I)
|